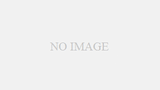東京近郊の方むけ、自撮りの手間がかからないフォーム撮影会にご参加ください。

駒沢公園
又は
皇居外苑
開催概要
このホームページ又はモシコムからも申し込めます。
フォーム撮影会
2025年10月から12月の開催日程
10/4(土)13:00-14:00(駒沢公園 又は 皇居行幸通り広場)- 10/11(土)13:00-14:00(駒沢公園 又は 皇居行幸通り広場)
- 10/18(土)13:00-14:00 (駒沢公園 又は 皇居行幸通り広場)
- 10/25(土)13:00-14:00 (駒沢公園 又は 皇居行幸通り広場)
- 11/1(土)13:00-14:00 (駒沢公園 又は 皇居行幸通り広場)
- 11/8(土)13:00-14:00 (駒沢公園 又は 皇居行幸通り広場)
申し込み1名様から開催します。
撮影場所を駒澤公園から変更可能です
申し込みの早い方の都合により開催場所を駒沢公園から皇居に変更可能です
標準:駒沢オリンピック公園 中央広場(タワーのあるところ)
〒154-0013 東京都世田谷区駒沢公園1−1
オプション:皇居外苑行幸通り地上
東京駅丸の内側から皇居に向かう行幸通り地上皇居側

開催詳細
撮影の概要:
- ウォーミングアップの後にカメラの前を最大5回、50m程度走っていただきます。
- 1人づつ時間をずらしながらの撮影。
- 所要時間は説明や準備含め30分から1時間以内で終了いたします。
- 肩と腰にテープを貼りマークとします(主催者で用意します)
- 服装は肌に密着したものが望ましく(計測のため身体の線を出したい)
- 上着とパンツは異なる色のものが望ましい
(上着の裾をパンツに入れて腰を露出させます)
同系色の場合は、後の腰骨の位置にテープを貼ります。 - 耳をマークに使用するため、髪の長い方は帽子などで耳を出して下さい。
(帽子にマークをつける場合もあります) - 現地は着替えるテントなどはありませんので、事前にご用意をして集合ください。
更衣室は公園内の有料でありますので、使用する場合は各自ご負担願います
料金(キャンペーン価格1000円オフ)
一般 16000円/人
学生割 1000円 off
支払い方法
当日払い:現地での現金支払い
キャンセルについて
- キャンセルの場合は開催日(土)の3日前の水曜日まで担当者へ連絡をお願いします。
それ以降、当日でも必ず連絡をお願いいたします。
(受付後に、担当者連絡先をご連絡いたします) - 当日の無断キャンセルの場合は、別途キャンセル料金をお支払いいただく場合があります
開催条件(主催者側が中止と判断する条件)
- 参加1名でも開催いたします
- 撮影は天候に左右されますので、天気予報が当たらずに、当日の開催場所で雪・雨(小雨含む)・強風などが続く場合は、当日であっても中止させていただきます。
- 主催者側都合で(交通渋滞や緊急の事態などのため)開催ができ無い場合
(お客様との相談の上、撮影会の日程を調整変更させていただきます)